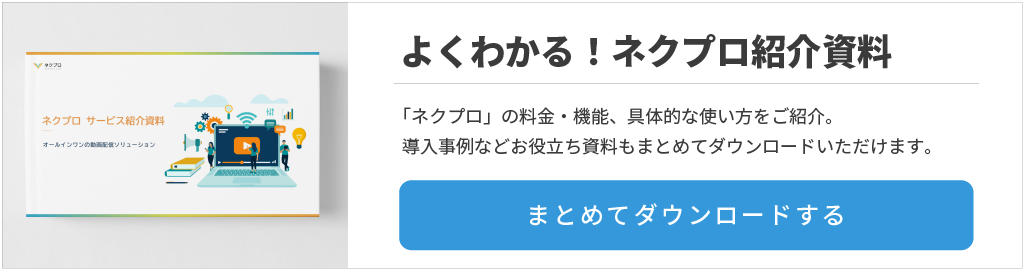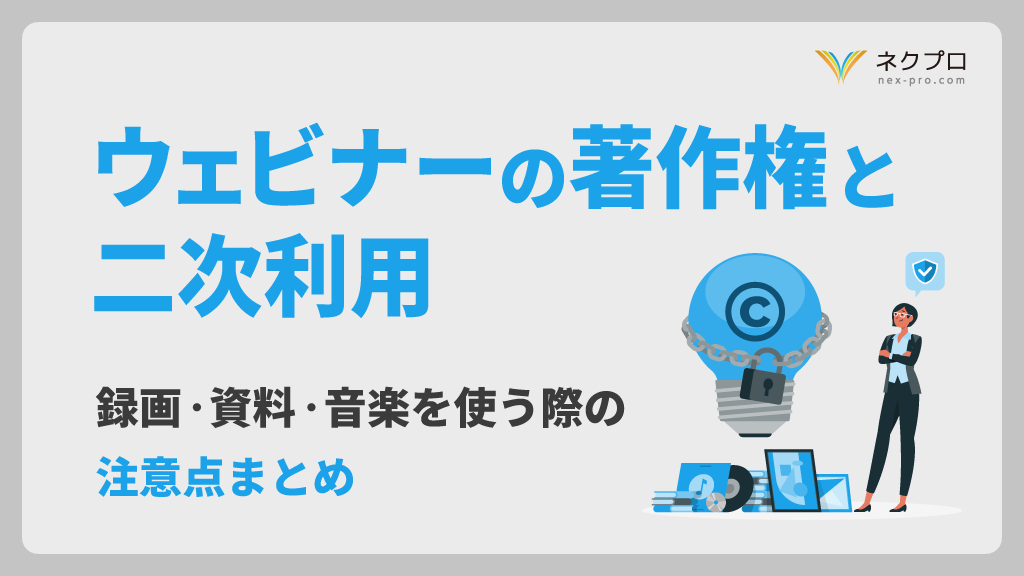
オンラインセミナー(ウェビナー)は企業の情報発信手段としてますます重要性を増しています。製品・サービスの紹介、顧客教育、リード獲得など、あらゆる場面でウェビナーは使われていますが、その一方で主催者の頭を悩ませるのが「著作権」や「二次利用」の問題です。
例えば以下のような疑問を抱いたことはないでしょうか?
- 他人の画像をスライドで使っても問題ない?
- ウェビナーの録画を自社サイトやYouTubeで公開してもいい?
- 講師や外注が作った資料を、自社のコンテンツとして再利用してもよい?
これらの疑問はすべて「著作権」に関係しています。本記事では、ウェビナーにおける著作権の基本と、録画・資料・音楽・画像などをどこまで二次利用できるかについて、実務的かつ法的な観点から整理します。
目次
ウェビナーで著作権が問題になる理由
ウェビナーはライブ配信であれ録画配信であれ、第三者に向けてコンテンツを公開・共有する行為です。そのため、使用する画像、動画、音楽、資料などに著作権が存在する場合は、正当な利用方法を踏まえていないとトラブルに発展するリスクがあります。
著作権とは、「創作された表現」に対して自動的に与えられる権利です。そしてこの権利には大きく2種類あります:
- 著作財産権:複製、上演、公衆送信、展示など、経済的利益をもたらす行為を制御できる権利
- 著作者人格権:作品の改変や著作者名の表示について、人格的利益を守る権利
「著作権」とは、「著作物」を創作した者(「著作者」)に与えられる、自分が創作した著作物を無断でコピーされたり、インターネットで利用されない権利です。
――「著作権って何?(はじめての著作権講座 )」より引用
つまり、たとえ「社内で作ったスライド」や「無料で拾った画像」だったとしても、それらが他人の著作物である場合は、無断使用によって著作権侵害となる可能性があります。特にウェビナーは不特定多数に配信されるため、一般的な社内資料よりも一段高いコンプライアンス対応が求められます。
ウェビナーで使う音楽や画像の著作権に要注意

音楽の使用と著作隣接権
音楽を使用する場合、「著作権」だけではなく「著作隣接権」も関係します。具体的には以下のような関係者が権利を持ちます:
- 作詞・作曲者:著作権
- 歌手や演奏者:実演家の権利(著作隣接権)
- レコード会社や配信会社:原盤権(著作隣接権)
つまり、楽曲をウェビナーで流したり、録画動画に音楽を挿入したりする際は、JASRAC等の団体への申請だけでなく、原盤権者への許諾取得も必要です。
著作物の公衆への伝達に重要な役割を果たしている者(実演家,レコード製作者,放送事業者及び有線放送事業者)に与えられる権利
――文化庁「著作隣接権」より引用
画像やイラストも要注意
画像検索で見つけた写真や、ネット上に掲載された図表、マンガやアニメの一コマなども、基本的には著作物として保護されます。「引用だからOK」と思っていても、条件を満たしていないと単なる無断使用と見なされます。
- 一瞬表示されるだけでも、商用配信であれば問題視されることがある
- 編集して使っても、元の著作物を特定できれば著作権侵害となる可能性あり
ウェビナー資料やスライドの二次利用はどこまで可能?
多くの企業が、ウェビナーの録画やスライド資料を「二次利用」したいと考えています。具体的には以下のような活用シーンが想定されます:
- 録画アーカイブとしてオンデマンド配信(リード獲得や営業支援)
- スライドを資料化してホワイトペーパーとして配布
- 内容を一部抜粋して、ブログ記事やSNSに転用
しかし、これらの再利用にはいくつもの法的・実務的なハードルがあります。
よくある問題点:
- 社員が作ったつもりの資料でも、著作権が個人に帰属している場合がある(参考)
- 外部講師や共同開催者のスライドは、自社では再利用できないことが多い
- 資料内に使用されている画像やグラフが他社提供のものであることに気づいていない
チェックリスト:
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| 🔹 著作権の帰属確認 | 制作物の権利者は誰か(社内・外注・講師) |
| 🔹 再利用の契約条項 | 再配信・編集・販売の許諾が契約に含まれているか |
| 🔹 他社素材の使用有無 | フリー素材か、使用条件を満たしているか |
ウェビナーを二次利用してオンデマンド動画として活用したい方はこちらもご覧ください。
著作物を合法的に引用するための3つのルール
引用は、著作物の一部を「例示」や「批評」「紹介」などの目的で使う場合に認められる制度です。ただし、適切に行われなければ違法とみなされるため、次の3つの条件を必ず満たす必要があります。
- 出典が明確であること(一次情報から引用)
- 主従関係が明確であること(引用がメインではない)
- 引用部分が明確に区別されていること(色・カギカッコ・レイアウト)
公表された著作物は、引用して利用することができます。この場合、その引用は公正な慣行に合致し、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければなりません。
――「著作権法」より引用
著作権を気にせず配信・二次利用する方法

著作権トラブルを回避しつつ、安心してウェビナーを配信・再利用するためには、以下の方法が有効です。
方法1:ロイヤリティフリー素材の活用
- 音楽:DOVA-SYNDROME、OtoLogic
- 画像・動画:Pixabay、Pexels、Unsplash
- イラスト:ソコスト、イラストAC
商用利用や改変が可能かどうかを、利用前にしっかりと確認しましょう。
方法2:完全自社制作
- スライド、図表、写真、動画などをすべて内製する
- 外注制作の場合は「著作権譲渡」または「利用許諾」の契約を取り交わす
ウェビナー録画・アーカイブ活用時の注意点
録画したウェビナーをアーカイブとして残したり、動画コンテンツとして再編集したりする際にも、以下のような注意点があります。
- 登壇者の同意:録画・再配信・資料再利用について契約書や同意書に明記
- 視聴者のプライバシー:参加者の名前や顔が映っている場合、公開範囲に配慮
- 共催者・協賛者との調整:著作物の帰属と公開範囲を事前に共有
FAQ:よくある質問とその回答
Q. YouTubeでウェビナー録画を公開したい。問題ない?
A. 自社で制作し、すべての素材の著作権をクリアしていれば可能です。ただし、登壇者の許諾が必要です。
Q. 外部講師の資料を使って、別のウェビナーで再利用したい。
A. 講師本人の許諾または契約上の権利譲渡が必要です。原則NGと考えるべきです。
Q. 社員が作った資料は自動的に会社のもの?
A. 就業規則や雇用契約に「職務著作」として著作権が会社に帰属することが明記されていなければ、社員が著作権を持つケースもあります。
まとめ
ウェビナーの活用において、著作権の理解と適切な運用は、ブランドイメージの維持・法的リスクの回避・コンテンツ資産の最大活用に直結します。
再確認したいポイント:
- ✅ すべてのコンテンツの著作権帰属を明確にする
- ✅ 再利用を前提に、登壇者・外注との契約を整備する
- ✅ フリー素材でも利用条件を必ず確認する
- ✅ 引用は条件を満たしたうえで適切に行う
「気づかずに使っていた」が命取りにならないよう、社内でのガイドライン作成・教育・契約整備を進めることが今後ますます重要になります。上記を参考にしながら魅力的なウェビナー・動画コンテンツを作成していきましょう。
1つの動画を有効活用できるオンデマンド動画について、こちらもご覧ください。